「ドラム、叩いてみたい!」
そう思った瞬間、あなたはもうドラマーとしての才能を開花させ始めています!
ドラムはステージの一番後ろからバンド全体を支える、いわば「縁の下の力持ち」。華やかなギターやボーカルに比べると、どうしても目立ちにくいポジションです。そんな中でドラムのカッコよさに気づけるなんて、それだけで素晴らしいセンスの持ち主だと断言できます!
でも、いざドラムと向き合ってみると、こんな疑問が湧いてきませんか?
- 太鼓やシンバルがいっぱいあるけど、どれが何なの? どう叩くの?
- 楽譜がピアノとかと全然違う…どうやって読むんだろう?
- そもそも、それぞれの楽器にどんな違いや役割があるの?
この記事を読めば、そんなあなたの疑問はすべて解決します!
ドラムという楽器の全体像から、一つ一つのパーツの名前と役割、さらには基本的な楽譜の読み方まで、この記事でバッチリ分かります。
これからドラムを始めたい方も、基本をおさらいしたい経験者の方も、ぜひ最後まで読んで、ドラムの世界への第一歩を踏み出しましょう!
そもそもドラムとは?
ドラムセットとは、「いろいろな種類の太鼓やシンバル(打楽器)を集めて、一人で演奏できるようにセッティングしたもの」 です。
たくさんの楽器が集まっているので、それぞれに名前と役割があります。
どんな楽器をどう組み合わせるかは、ドラマーの自由! もちろん基本的なセッティングはありますが、「こんな音が出したい!」というアイデア次第でパーツを増やしたり変えたりできるのも、ドラムの大きな魅力なんです。
ドラムセット全体の役割は、大きく分けて2つあります。
- バンド全体のリズムの土台となること
ドラムがしっかりとしたビートを刻むことで、他の楽器が安心して演奏できます。
- 音楽全体の抑揚(盛り上がりや静けさ)をつけること
曲の展開に合わせて力強く叩いたり、繊細なリズムを入れたりして、曲に表情を与えます。
まさにバンドの心臓部であり、ムードメーカー。「ドラムがしっかりしているバンドは良いバンド」と言われるほど、音楽のクオリティを左右する重要な楽器なんです。
ドラムセットの基本構造
まずは、一般的なドラムセットの構成と、それぞれの名前を見ていきましょう。

大体こんな感じの組み合わせが基本です。では、それぞれのパーツを詳しく見ていきましょう!
バスドラム
特徴
ドラムセットの中で一番大きな太鼓。一番低い音が出ます。ペダルを使って「足」で演奏するのが最大の特徴です。
役割
リズムの最低音部を担当し、曲の根幹となるビートを支えます。足で踏むためパワフルな音が出せ、リズムの土台として非常に重要。「ドッ」「ドン」という力強い音で、曲に安定感を与えます。
歴史的ポイント
足でバスドラムを演奏できるようになったことで両手が自由になり、ドラムセットが一人で多くの打楽器を演奏できる形に進化したと言われています。
スネアドラム
特徴
奏者の正面やや左(右利きの場合)に置かれることが多い小太鼓。裏側に「スナッピー」と呼ばれる響き線が付いていて、「タンッ」「スパッ」という歯切れの良い、明るく華やかな音がします。
役割
ドラムセットの主役とも言える存在。特にポピュラー音楽では、2拍目と4拍目(バックビート)を叩いて曲にノリを生み出すことが多いです。フィルイン(曲のつなぎ目に入れるフレーズ)でも存在感を発揮し、曲を彩ります。叩く頻度も非常に高く、なくてはならない楽器です。
ハイハットシンバル
特徴
奏者の左手側(右利きの場合)にある、2枚のシンバルを組み合わせたもの。「ハイハットスタンド」というペダル付きのスタンドに取り付けられています。
役割
主にリズムを細かく刻む役割を担います。
例えば8ビートなら、「チッチッチッチッ」と8分音符を刻むことが多いです。ペダルの踏み加減で、シンバルの開き具合を調整でき、「チッ」という短い音から「シャー」という開いた音まで、多彩な表現が可能です。ドラムセットの中で最も叩く回数が多い楽器です。
バスドラム・スネアドラム・ハイハット。この3つはドラムの基本リズムを作る上で特に重要度が高いため、合わせて「3点セット」と呼ばれます。ライブハウスやスタジオで「3点持ち込みで」なんて会話を聞くこともあるので、覚えておくと便利です!
タム(タムタム)
特徴
スネアドラムと違い、スナッピーが付いていない太鼓です。「ドン」「トン」といった、太鼓らしい音がします。バスドラムの上に取り付けられることが多く、大きさによって音の高さが変わります。小さい方(高い音)を「ハイタム」、大きい方(低い音)を「ロータム」と呼ぶのが一般的です(3つ以上セッティングする場合もあります)。
役割
主にフィルインで使われ、メロディのようなフレーズを叩くことで曲に彩りや変化を与えます。「トンドン」「タカドコ」といったフレーズは、タムが活躍していることが多いです。
フロアタム
特徴
その名の通り、床(フロア)に直接置かれる、足付きの大きなタム。ハイタムやロータムよりもさらに大きく深いため、「ドン」「ドゥン」といった低く力強い音が出ます。
役割
タムと同様にフィルインで使われるほか、ハイハットやライドシンバルの代わりにフロアタムでビートを刻むこともあります。これにより、非常にパワフルで重厚なリズムを生み出すことができます。
ライドシンバル
特徴
奏者の右手側(右利きの場合)に置かれることが多い、大きめのシンバル。サスティーン(音の伸び)が長く、落ち着いた音が特徴です。
役割
名前の由来(Ride on the beat = ビートに乗る)の通り、ハイハットと同じようにリズムを刻むのが主な役割です。特にジャズではライドシンバルでリズムを刻むのが定番。ロックやポップスでも、ハイハットとは違う雰囲気のリズムを出したい時に使われます。シンバルの中心部分(カップ/ベル)を叩くと、「カーン」という硬く高い音が出ます。リズムを刻む以外にも、曲のアクセントとしてクラッシュシンバルの代わりに叩くこともあります。
クラッシュシンバル
特徴
ドラムセットの中で比較的高めの位置に、左右に1枚ずつ(またはそれ以上)セットされることが多いシンバル。「シャーン!」「ガシャーン!」といった、華やかでインパクトのある音がします。ライドシンバルよりはサスティーンが短めです。
役割
「クラッシュ」の名前の通り、曲の盛り上がりや場面転換など、アクセントをつけたいタイミングで叩くのが主な役割です。サビの頭などで鳴らすと、曲が一気に華やかになります。ハードロックなどでは、ビートを刻むために連続して叩くこともあります。
その他の楽器
基本的なセットは以上ですが、ドラムの世界はもっと自由!
エフェクトシンバル
チャイナシンバル(歪んだような独特な音)、スプラッシュシンバル(「シャッ」と短い音)、スタックシンバル(複数のシンバルを重ねてノイジーな音)など、個性的な音を加えるシンバルもたくさんあります。
パーカッション類
カウベル、ウッドブロック、タンバリンなどをセットに組み込んで、サウンドの幅を広げるドラマーもいます。
タムをたくさん並べたり、バスドラムを2つ使う「ツーバス」セッティングにしたり、見た目もサウンドも自分好みにカスタマイズ可能です。
タムをたくさん並べたり、バスドラムを2つ使う「ツーバス」セッティングにしたり、見た目もサウンドも自分好みにカスタマイズ可能です。
どんな音を出したいか、どんな音楽をやりたいかに合わせて、無限の組み合わせが考えられます。ぜひ、あなただけの「カッコいい!」と思えるセッティングを追求してみてください!
ドラム楽譜の読み方【基本編】
さて、ドラムのパーツが分かったところで、次は楽譜の読み方に挑戦してみましょう! ピアノやギターの楽譜とは少し違う、ドラムならではのルールがあります。
ドラムの楽譜は、基本的には五線譜を使って書かれます。でも、音階(ドレミ)を表すのではなく、「どの楽器を叩くか」 を示しているのが大きな特徴です。以下、それぞれの楽器の表記の仕方です。

実は、ドラム譜の書き方には「絶対にこれ!」という世界共通の厳密なルールがあるわけではありません。もちろん、大まかな「約束」はありますが、楽譜を書く人や出版物によって、どの位置にどの楽器を割り当てるか、記号の使い方が微妙に異なる場合があります。
初めて見る楽譜の場合は、音源を聴きながら「この音符はこの楽器の音だな」と耳で確認する ことがとても大切です! 慣れてくれば、だいたいのパターンは読めるようになります。
まとめ
今回は、ドラムセットの基本的な構造や各パーツの役割、そしてそれぞれの打楽器の楽譜の読み方について解説しました。
ドラムは、バンドのリズムとグルーヴを一手に担う、本当に重要でやりがいのある楽器です。地味なんて言わせません! ドラムがいるからこそ、バンドサウンドは輝くんです。
この記事でドラムの基本が分かったら、次はぜひ実際にスティックを握って、音を出してみてください。最初はただ音を鳴らすだけで大丈夫! 生音の迫力を体験することで、ドラムという楽器の素晴らしさに気付きます。
ドラムの世界は奥深く、知れば知るほど、叩けば叩くほど、その魅力にハマっていくはず。
この記事が、あなたのドラマーへの道の足掛かりになることを期待しています。
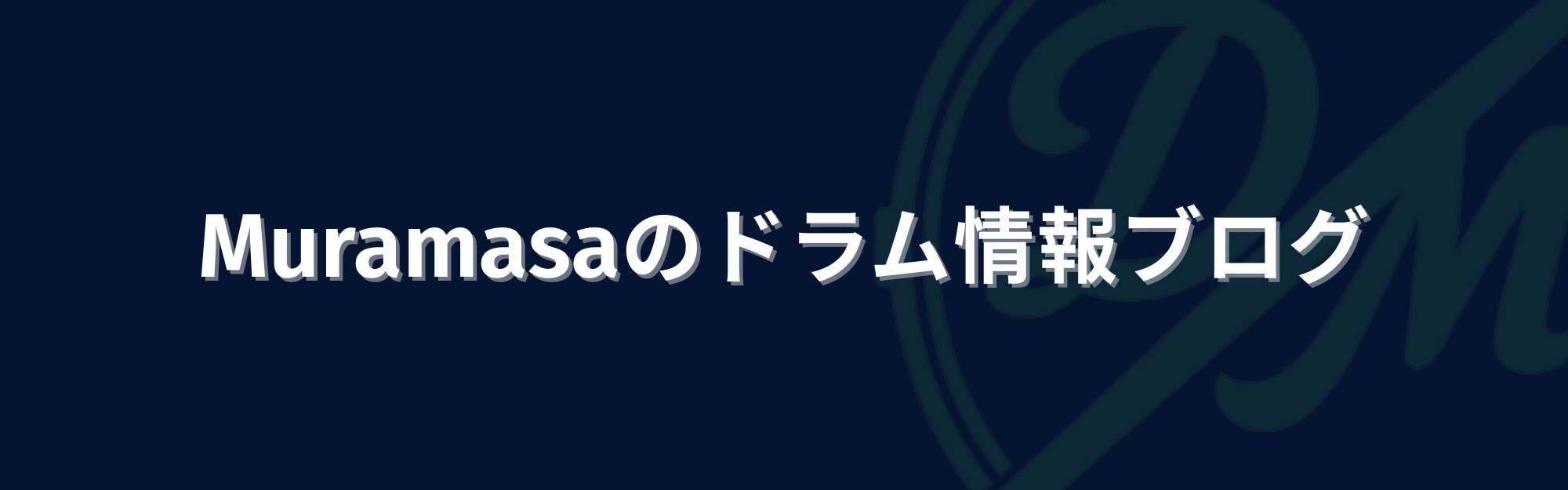


コメント