- 「速い8ビートが叩けない…」
- 「好きな曲のテンポについていけず、挫折してしまう…」
ドラムを練習していると、誰もが一度はぶつかる「スピードの壁」。叩きたい曲があるのに、身体がついてこない悔しさ、痛いほど分かります。私も昔は練習しては速く叩きたい一心で練習に打ち込んでいましたが、なかなか上手くいかずにもどかしい日々を送っていました。しかし、今回紹介する「アップダウン奏法」が習得できたことを機に、今まで限界だと感じていたテンポの曲が楽に叩けるようになりました。
今回は8ビートのスピードアップに直結する奏法である「アップダウン奏法」について解説します。
- アップダウン奏法とは
- アップダウン奏法を習得するメリット
- アップダウン奏法の練習方法
- アップダウン奏法を練習する際のポイント
アップダウン奏法の習得は、スピードアップを目指す全てのドラマーにとって避けては通れない道です。この記事を読み終える頃には、あなたも「スピードの壁」を乗り越えるためのヒントを掴んでいます。
習得するのは簡単ではありませんが、スピードアップを目指すドラマーにとって、この記事がアップダウン奏法にチャレンジするきっかけになれば幸いです。
アップダウン奏法とは?
「アップダウン奏法」とは一言で言えば、「アップストロークとダウンストロークを組み合わせ、1回の腕の振り(上下運動)で、2回叩く奏法」です。
- ダウンストローク:スティックを高いところから振り下ろし、打面にヒットした後は低い位置で止めるスティックを止めるストローク
- アップストローク:スティックを低い位置から落として小さな音を出し、その後にスティックを振り上げて、高い位置へと持っていくストローク
アップストロークとダウンストロークの詳細は以下の記事を参照願います。
ダウンストロークでスティックを振り下ろして1音。その後、アップストロークでスティックを振り上げる際に1音。この2つのストロークを組み合わせることで、スティックが元の位置から一往復する中で2打の音を出すことが可能になるのです。これが「アップダウン奏法」になります。
アップダウン奏法を習得する3つのメリット
アップダウン奏法を身につけることは、スピードアップだけでなく、様々なメリットがあります。以下、3つのメリットを説明します。
8ビートのスピード向上
最大のメリットは、8ビートのスピードが飛躍的に向上することです。
従来の1打ごとに腕を上下させるストロークでは、BPM180を超えるような高速8ビートを叩き続けるのは至難の業です。しかし、アップダウン奏法を使えば、腕の運動量が実質半分になるため、これまで不可能だと感じていたテンポにも対応できるようになります。速い曲を演奏するプロドラマーのほとんどが、この動きを自然に取り入れています。
脱力した叩き方が身に付く
アップダウン奏法は、力を抜いてスティックを落とす「ダウンストローク」と、力を少しだけ加えてスティックを引き上げる「アップストローク」を繰り返す奏法です。力を抜くことが重要になるため、余分な力を加えないようにする練習としても最適です。慣れるまでは腕に力が入って疲労を感じることでしょう。しかし、一度腕の力を抜いて叩くことを身体が覚えてしまえば、腕にかかる負担が軽減され、長時間でも安定したパフォーマンスを維持できます。
強弱のメリハリがつき、表現力が生まれる
初心者の方によくある症状として、「ハイハットの音が目立ちすぎて、悪目立ちしてしまう」というものがあります。この症状を改善するためにも、アップダウン奏法は非常に有効です。アップダウン奏法は、自然と「強・弱・強・弱」のダイナミクス(強弱)が生まれるため、ビートに心地よい抑揚がつきます。
強いダウンストロークでビートの核を作り、弱いアップストロークでグルーヴの隙間を埋める。これにより、アンサンブル全体に立体感が生まれ、「ただ速いだけ」ではない、音楽的なドラミングが可能になるのです。
アップダウン奏法の具体的な練習方法
実際にどのように練習すれば良いのか解説します。正しいフォームを身体に覚えさせるため、段階的に進めていきましょう。
STEP 1: ダウンストロークとアップストロークを続けて練習する。
まずはダウンストロークとアップストロークの動きを身体に染み込ませます。まずは練習台やスネアドラム等、叩きやすい場所でスタートすると良いです。BPM=60くらいのゆっくりとしたテンポから、ダウンストローク→アップストローク→ダウンストローク…の順に丁寧に叩いていき、慣れてきたらテンポを上げていきましょう。ダウンストロークの際に力を入れずに、腕を落とすだけという感覚が得られてきたら、脱力も身についている証拠です。
STEP 2: ハイハットで実践してみる
基本動作に慣れてきたら、ハイハットを使ってアップストロークとダウンストロークを叩いてみましょう。基本動作は同じですが、ハイハットを叩く際にはポイントがあります。ダウンストロークは、スティックのショルダーの部分でハイハットのエッジ(シンバルの縁)を叩き、アップストロークでは、スティックのチップ(先端)でハイハットのトップ(天面)を軽く叩きましょう。ハイハットの叩き分けを意識することで、音量だけでなく音色にも差が生まれ、より立体的なビートになります。
STEP 3: スネアドラムとバスドラムを追加する
ハイハットが安定してきたら、通常の8ビートと同じように、スネアドラムとバスドラムを加えてみましょう。右手はアップダウンで8分音符を刻みながら、手足のタイミングを合わせていきます。
スネアドラムやバスドラムを交えてアップダウン奏法を練習する時によくある症状が、利き手以外の動きが入ると、全身に力が入ってしまうというものです。この症状はそれぞれ独立して動かそうとしていることに起因します。それぞれの手足がどこで一致しているのか確認しながら、1つのビートとして捉え、動きが連動するようになれば、自然と身体の力も抜けてきます。脱力の感覚が身に付くまで、しっかりと練習しましょう。
アップダウン奏法を練習する際のポイント
練習の効果を最大化するために、以下の4つのポイントを常に意識してみてください。
ゆっくりしたテンポから動きを確認する。
アップダウン奏法を身につける目的の多くが、「8ビートを速く叩きたい」という気持ちです。速く叩きたいという想いから、どうしても無理のあるテンポで練習をしてしまう人がとても多いです。しかし、その早く上達したいという気持ちをぐっとこらえ、まずはゆっくりとしたテンポから、一打一打の動きと音を確かめましょう。腕がしっかり脱力できているか、余分な力が入っていないかを確認しながら、動きを身体にしみ込ませましょう。
腕全体を大きく使う意識を持つ
アップダウン奏法を使用しているドラマーを見ると、手首が上下していることが確認できます。そのため、アップダウン奏法は手首を上下に動かすテクニックと思われがちです。しかし、重要なことは腕全体を使って演奏する事です。講師としてアップダウン奏法を教えているときに、手首だけを動かそうとして、肘や肩に力が入ってしまい、結果的に腕の自然な動きが阻害されている生徒を数多く見てきました。上手く力が抜けないという人は、一度手首だけではなく、肘や肩の動きにも注目してみましょう。
「力を入れる・抜く」のメリハリを意識する
アップダウン奏法の最大のコツは「脱力」にあります。特に、ダウンストロークでは、力を抜いて、「スティックを持った腕をそのまま落とす」くらいの気持ちで叩きましょう。ダウンストロークに対してアップストロークでは、スティックを引き上げるためだけに少し力を使ってあげます。このアップダウンの繰り返しを経て、アップダウン奏法は完成します。力の入れどころを間違えないよう、十分に確認しながら練習しましょう。
動画を撮影して客観的にチェックする
アップダウン奏法を使いこなしているドラマーの動きはどこか共通点が見えます。アップダウン奏法が上手くいかないなと感じたら、自分のフォームをスマートフォンなどで撮影し、客観的に自分の動きを分析してみましょう。
自分の好きなドラマーや、上手なドラマーの動画と、自分のフォームw比較することで、改善点が明確になります。動画撮影をして振り返ることこそが上達への近道です。
まとめ
今回は、8ビートの高速化に不可欠な「アップダウン奏法」について、その理論から具体的な練習方法、練習のポイントまで解説しました。
アップダウン奏法は、理論が分かったからと言ってすぐに出来るものではありません。地道な反復練習が習得には必要になります。しかし、習得することでスピードアップになるだけではなく、表現力豊かなドラミングが手に入り、一生モノの財産になることを私は保証します。
この記事が、あなたの8ビートの高速化に役立てば幸いです。簡単なテクニックではありませんが、習得することであなたのドラムライフが大きく動き始めることでしょう。
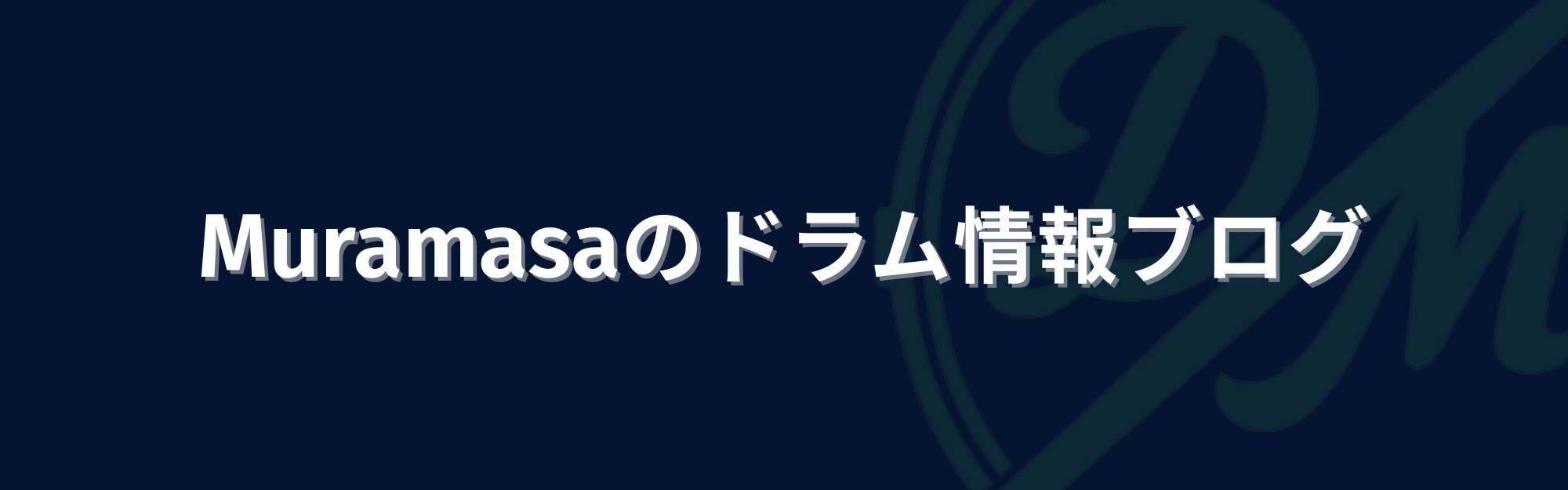
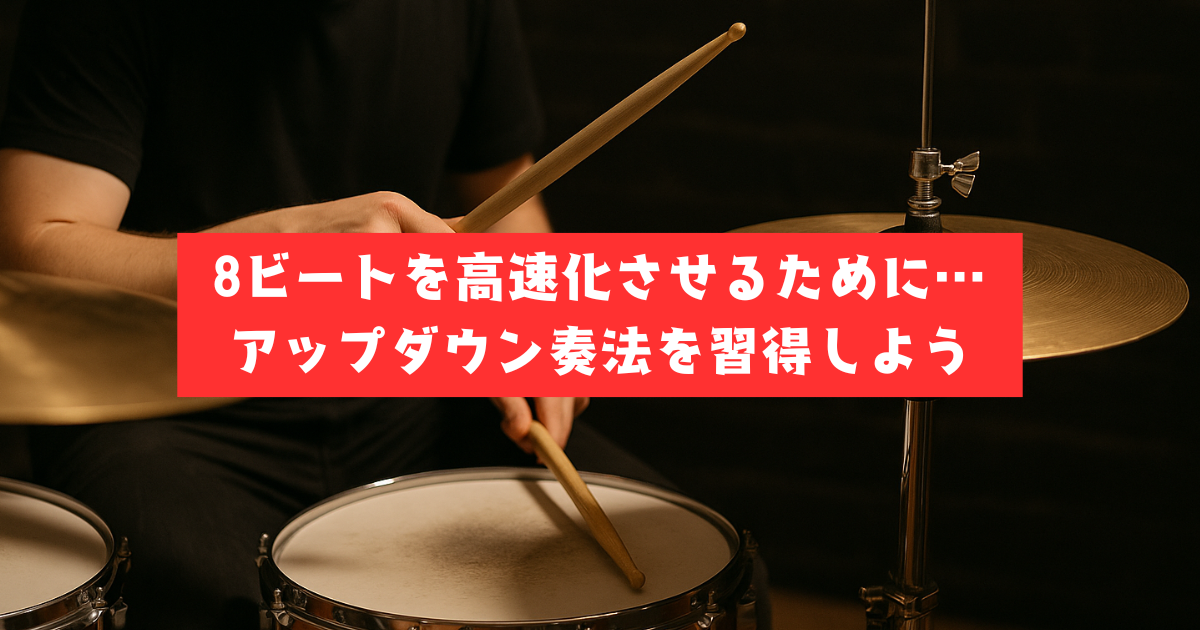


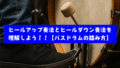
コメント