- 「バスドラムの踏み方って何が正解なんだろう…」
- 「バスドラムの踏み方って色々あるけど、何が違うの?」
ドラムを始めたばかりの方なら、一度はそう感じたことがあるのではないでしょうか。バスドラムはペダルを踏んで鳴らす楽器なので、「どうやって踏んだら良いのか?」「ただペダルを踏めば音が出るから、それで良いのでは?」と思う方も多いと思います。しかし、バスドラムはペダルの踏み方1つで大きく音が変わる楽器です。バスドラムの奏法に関する悩みを解決すべく、今回はバスドラムの基本的な2つの踏み方である、「オープン奏法」と「クローズ奏法」について現役のドラム講師が徹底的に解説します。
- オープン奏法・クローズ奏法の概要
- オープン奏法とクローズ奏法の違い
- オープン奏法とクローズ奏法のどちらを先に習得すべきか
- オープン奏法とクローズ奏法を習得するメリット
- オープン奏法とクローズ奏法の練習する際のポイント
オープン奏法、クローズ奏法の特性を理解することで、自分が出したい音に対する適切なアプローチが可能になります。安定感と表現力を両立させた、理想のフットワークを手に入れて、ドラムライフをより充実したものにしましょう!
オープン奏法とは
オープン奏法とは、バスドラムを叩いた直後にビーター(ヘッドを叩く先端部分)を打面からすぐに離す奏法です。ビーターをバスドラムから離すことで、バスドラムがミュートされることを防ぎ、バスドラムの持つ豊かな響きと余韻を最大限に活かすことが出来ます。オープン奏法はバスドラム本来の伸びやかで、ふくよかな温かいサウンドを出すことに適した奏法と言えます。
クローズ奏法とは
クローズ奏法とは、オープン奏法とは対照的に、バスドラムを叩いた後もビーターを打面に押し付けたままにする奏法です。ビーターをバスドラムのヘッドに付けたままにすることで、ヘッドの振動を意図的に押さえ、余韻をなくします。クローズ奏法は余韻を少なくすることで、輪郭がハッキリとしたタイトな音を出す時に適した奏法と言えます。
オープン奏法とクローズ奏法の違い
オープン奏法とクローズ奏法の違いは、単にビーターを「離す」か「付ける」かだけではありません。サウンドやプレイの感覚に大きな影響を与えます。
音色面
オープン奏法はビーターを離すことでヘッドが自由に振動し続けるため、低音が豊かで余韻の長い、ふくよかな音になります。ジャズやバラードなど、楽器全体の鳴りやアンサンブルとの調和が求められる音楽に適しています。
オープン奏法に対してクローズ奏法はビーターを押し付けることで余韻がカットされ、ビーターとヘッドが当たった際のアタックが強調された、タイトで輪郭のはっきりした音になります。ロックやメタルなど、速いテンポの中でも他の楽器に埋もれないパワフルなキックサウンドが必要なジャンルで多用されます。
ロックのような大音量の音楽でもオープン奏法を使って、あえて余韻を出すこともあります。逆に、繊細な音楽をしているときでもアクセントとしてクローズ奏法を使うこともあります。場面場面に応じて適切に使い分けましょう。
コントロール面
オープン奏法は踏んだ後に力を抜き、ビーターが自然に跳ね返る動きに合わせるため、足首の繊細なコントロールと脱力が求められます。足が地面に踏ん張るような体勢になれないため、慣れないうちは体が不安定になりやすいという側面もあります。
一方、クローズ奏法は踏み込んだ後も足でペダルを押さえ続けるため、その足が体を支える支点となり、演奏中の姿勢が安定しやすいというメリットがあります。動きがシンプルで、初心者でもパワーを伝えやすいのが特徴です。一方、足に力が入りやすく、適切な力感で演奏を続けることが難しいという側面もあります。
以上をまとめた表が下記になります。
| 項目 | オープン奏法 | クローズ奏法 |
|---|---|---|
| 音色面 | 低音が豊かで余韻の長い、 ふくよかな音。 | アタックが強調された、タイトで輪郭のはっきりした音。 |
| コントロール面 | 足首のコントロールと脱力が必要。体勢が不安定になりやすい。 | 演奏中の姿勢が安定しやすく、コントロールが容易。力が入りすぎるデメリットもあり。 |
ヒールアップ奏法、ヒールダウン奏法と組み合わせられる
オープン奏法、クローズ奏法の他に、「ヒールアップ奏法」と「ヒールダウン奏法」という奏法もあります。
- ヒールアップ奏法:演奏時にかかとをペダルから浮かせて足全体を持ち上げ、その後、力を抜いて足を踏み下ろすバスドラムの奏法
- ヒールダウン奏法:かかとをペダルにつけたままペダルを操作してバスドラムを演奏する奏法
ヒールアップ奏法、ヒールダウン奏法それぞれ奏法の中で、オープン奏法、クローズ奏法の2種類の奏法を選択できます。そのため、バスドラムの踏み方は2×2通りの踏み方があるということです。
ヒールアップ奏法とヒールダウン奏法については以下の記事を参照願います。
まずはクローズ奏法を習得しよう
「オープン奏法とクローズ奏法のそれぞれの特性は分かったけど、どっちから練習すればいいの?」と疑問に思う方もいるでしょう。私は、まずクローズ奏法から練習することを強くお勧めします。それには明確な理由があります。
安定感を得やすい
クローズ奏法は踏み込んだ足で体を支えることができるため、演奏フォームが安定しやすい奏法です。慣れないうちはまずクローズ奏法で地に足がついている感覚を持ちながら練習することで、上半身への安心感にも繋がります、
動きが単純で、習得しやすい
ヒールダウン奏法は「ペダルを踏み込み、そのままビーターを押し付ける」奏法であり、動きとしては足を踏み下ろすだけの非常にシンプルな奏法です。オープン奏法のように「踏んだ後に力を抜いて戻す」という複雑なコントロールが不要なため、初心者の方でも感覚を掴みやすいのです。
アタックが強調されたパワー感のある音色を習得できる
特にロックやポップスなどでは、バスドラムの音色はしっかりと芯のある大きな音を出すことが大切です。クローズ奏法は、体重を乗せやすく、パンチのあるサウンドを得やすいため、バスドラムに求められる音色を出しやすい奏法になります。
世の中の多くのロックミュージシャンや著名なドラマーも使い分けはあるにしても、クローズ奏法で演奏することが非常に多いです。動画サイトなどで足の動きを確認してみましょう!
クローズ奏法の基本的な踏み方
では、クローズ奏法の基本的な踏み方を解説しましょう。ここでは、バスドラムの奏法としてポピュラーな「ヒールアップ奏法」と組み合わせて行うことを前提に解説します。
1.足を上げる
まずはヒールアップ奏法同様に、足を上げます。この時に足首、ふくらはぎ、太ももに余計な力を入れず、見えない糸で足を釣り上げるイメージで足を上げましょう。
2.足を落として踏み込む際に、ビーターをヘッドに押し付ける
上げた足をそのままストンと、重力を利用してペダルを踏み込むように落とします。ビーターとバスドラムのヘッドが当たった瞬間、少しだけ足先に力を加え、ビーターが跳ね返ってこないようにキープします。この時、グッと力を加えるのではなく、あくまで足の重みをペダルに預けるようなイメージで足を置きましょう。余分な力みはかえってスムーズな演奏を阻害しますので、できる限り力は抜いておきましょう。
クローズ奏法を練習する際のポイント
力任せに踏み込むのではなく、重力を利用する
クローズ奏法はビーターをヘッドに押さえつけるという奏法の特性上、足先にどうしても力が加わりやすいです。力をずっと入れたまま、力任せに踏み込んでいては、すぐに疲れてしまいますし、演奏もどこかぎこちないものになってしまいます。大切なのは、持ち上げた足の重さが自然にペダルに伝わる感覚です。上からストンと落とすイメージで踏み込んでみましょう。脱力する中で、力の適切な入れ具合を覚えていくことが大切です。
ビーターをヘッドに付けた後は、かかとを下ろして足を休ませる
ビーターをバスドラムのヘッドに押し付けて、次のアクションに入る前には、かかとを下ろしましょう。かかとが上がりっぱなしになっているのは、太もも、ふくらはぎに余分な力が入っている証拠です。力が入ったままでは次のアクションへスムーズに移行することができません。ビーターをヘッドに付けたあとは、ペダルに体重を預けて足をリラックスさせる意識を持ちましょう。次のキックの直前まで、足の力を温存しておくことが、安定した連打や長時間の演奏につながります。
特に初心者の方は、ビーターをバスドラムに押し当てた直後、かかとが上がったままになっている方が多いです。一度自分の足の動きを確認して、力が入ったままになっていないかチェックしましょう。
オープン奏法を習得するメリット
クローズ奏法で安定した土台ができたら、ぜひオープン奏法にも挑戦してみましょう。「クローズ奏法がよく使われるのであれば、オープン奏法はいらないのでは?」と思いますが、そんなことはありません。オープン奏法を習得することで、あなたののフットワークはより一層進化し、ドラミング全体に好影響を与えてくれます。ここではオープン奏法を習得するメリットを3つ紹介します。
脱力の感覚を覚える
オープン奏法は、インパクトの瞬間に力を抜くことで、ビーターとバスドラムのヘッドを離すことが肝心です。ビーターを押し付けるようなクローズ奏法とは違い、オープン奏法を通じて、足全体の余計な力みを抜き、リラックスして演奏する感覚が身につきます。結果的にクローズ奏法を演奏する時にも適切な力加減が分かり、双方向に良い影響が出てきます。
音色をコントロールする練習になる
オープン奏法を習得する最大のメリットは、バスドラム本来のふくよかなサウンドを出せるようになることにあります。オープン奏法を習得することで、クローズ奏法のアタックの強い音だけでなく、広がるようなバスドラムの音も表現できるようになります。クローズ奏法との使い分けまで出来るようになれば、あなたの表現の幅は格段に広がります。
連打をする際に、オープン奏法で学んだことが役に立つ
バスドラムのダブルや、それ以上の連打をするときに大切なことが、一度バスドラムを踏んだあと、リバウンドを利用してビーターの幅をしっかりと戻すことです。クローズ奏法の押し付ける奏法に慣れてしまうと、どうしてもリバウンドを活かすことができずに、2打目以降の音が小さくなる傾向にあります。リバウンドを活かすことに長けたオープン奏法を習得することで、連打をする時にもしっかりとビーター幅を稼ぐことができ、結果として安定した音色の演奏が可能になります。
オープン奏法の基本的な踏み方
オープン奏法の基本的な踏み方を解説しましょう。クローズ奏法と同様に、バスドラムの奏法としてポピュラーな「ヒールアップ奏法」と組み合わせて行うことを前提に解説します。
1.足を上げ、降ろす
クローズ奏法と同じように、足を持ち上げてペダルを踏み込みます。足を上げた時に、ビーターとヘッドが触れてしまうと不要な音が出てしまいます。不要な力を抜いて足を吊り上げるように上げましょう。
2.踏み込むことをせずに、ビーターを戻す
ビーターがヘッドに当たった瞬間、バランスが取りづらいこともあり、足先に力が入ってしまい、ビーターをヘッドに押し付けたくなります。ここで足先に力を入れることをせず、足首や足先の力を抜くイメージを持ちましょう。適切な脱力が出来ていると、ペダルのスプリングの力とヘッドの反発力で、ビーターが自然に手前に戻ってきます。ビーターがしばらくブラブラとすることが気になるかもしれませんが、慣れてくれば力を入れずにただ落とすだけでバスドラム本来の音を奏でられる、とても便利な奏法となります。
オープン奏法を練習する際のポイント
アタックの瞬間に力を入れない
最初はヒールダウン奏法で慣れてしまった足先の少し力を入れる動作がが出てしまったり、足の安定感を求めてどうしても踏ん張ってしまうでしょう。それほど、バスドラムを踏む際に力を入れないというのは難しいことです。最初はゆっくりとしたテンポでビーターがリバウンドを利用して返ってくることを確認しながら、力の抜き加減を覚えていきましょう。
足を上げる際にビーターとヘッドがつかないようにする
オープン奏法での力の抜き加減が分かり、ビーターを意図して戻すことができるようになっても、バスドラム1打だけで演奏が終わることはありません。ビーターがヘッドと離れた状態から、次のバスドラムの音を出すために足を上げた時、無意識にビーターがヘッドに触れてしまい、意図しない音が出てしまうことがあります。不用意な音が出るとせっかくの演奏が台無しになりかねません。ペダルから足を上げたときにビーターがヘッドに当たらないよう、力を抜いた動き方を身につけましょう。
足を上げるときにビーターとヘッドが当たってしまうのは、足を上げる瞬間に力みがある証拠です。足を釣り上げるイメージで、リラックスして足を上げられるように、繰り返し練習しましょう。
まとめ
今回は、バスドラムの基本となる「クローズ奏法」と「オープン奏法」について解説しました。
- クローズ奏法:アタックが強くタイトなサウンドで、演奏時の安定感を得やすい。
- オープン奏法:余韻が豊かでふくよかなサウンドで、表現力と脱力の技術が身につく。
どちらか一方が優れているというわけでは決してありません。大切なのは、両方の奏法を習得し、音楽が求めるサウンドに応じて自在に使い分けることです。
初心者の方は、まずクローズ奏法でしっかりとした土台を作り、自信がついたらオープン奏法で表現の幅を広げていってください。この2つの奏法の重要性と楽しさをが分かるようになれば、より表現の幅が広がり、よりドラムが楽しくなるはずです!
この記事が、あなたのフットワークををより表現豊かにする一助となれば、幸いです。ペダルに足を乗せて、新たな一歩を踏み出しましょう!
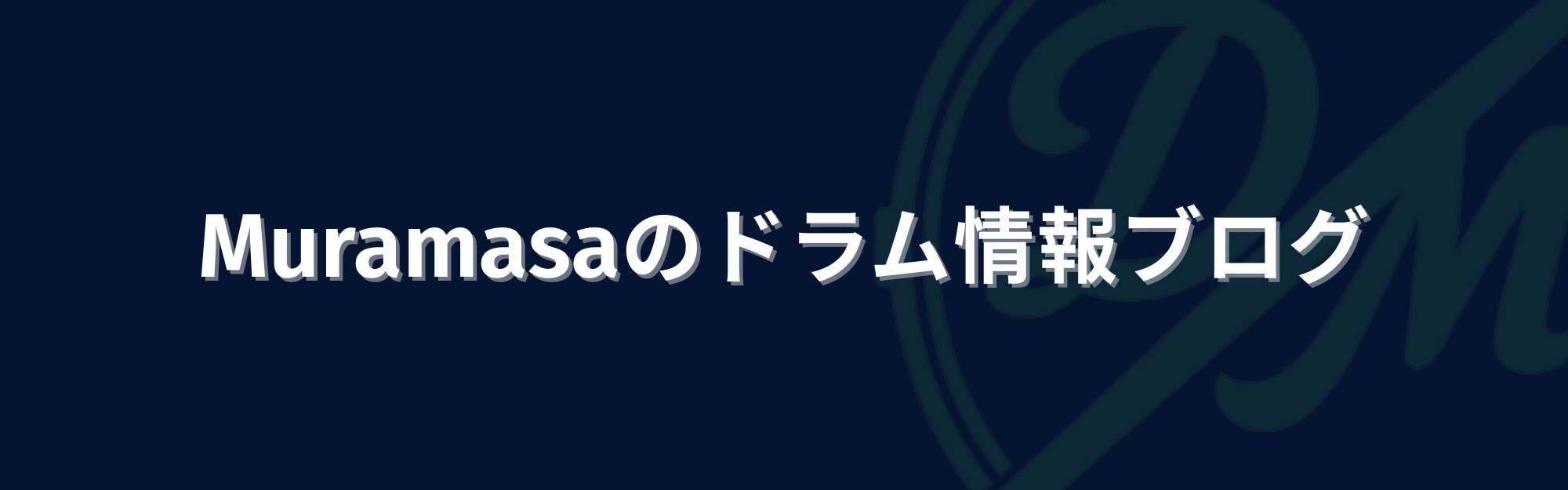

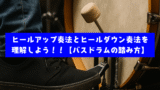
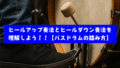
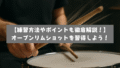
コメント